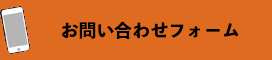秋田は昼間の気温がようやく2ケタで安定し始め、ようやく桜の開花が宣言されたところです。
ずっとひきこもりっぱなしだったので、思い立って散歩がてら近所の神社へ行ってきました。
実は今年まだ初詣に伺っていなかったんですよね…新年度を機に、ということで。
先日NHKの『日曜美術館』で紹介されていた東大寺の木造建築の話を思い出し、神社本殿の軒先に注目してみました。
NHK『日曜美術館』
まなざしのヒント 日本建築入門in東大寺・新薬師寺
初回放送日:2025年3月2日京都奈良を旅して国宝の仏像は見ても、国宝の建物は鑑賞ポイントがわからず、スルー…。そんなあなたのための「まなざしのヒント」。奈良・東大寺、新薬師寺の国宝建築を巡り、日本建築のイロハを学ぶ贅沢な授業。自由に描ける絵画と違い、建築は<重力との真剣勝負>。屋根の重さを支える構造美こそが最大の鑑賞ポイント。日本建築の特徴「組物」に注目し、時代で変わるデザインを紹介。日本人の美意識と木への愛情がそこにある!
本殿の柱から段々に突き出ているこの部分は「組物(くみもの)」と呼ばれ、重たい屋根の荷重をしっかりと柱に伝え、深い軒先を支えてる大切な構造です。

1段のものは「出組(でぐみ)」、2段なら「二手先(ふたてさき)」、そして3段になると「三手先(みてさき)」と呼ばれます。
手先が多いほど格式が高いとされ、金堂や層塔など重要な建物には三手先が使われることが多いそうです。
先日番組で取り上げられていた東大寺南大門は、なんと六手先(ろくてさき)!
そのおかげで、南大門はとても深い軒をしっかりと支え、堂々たる風格を生み出しています。
単なる装飾にとどまらず、機能性と美しさが一体となった日本の伝統木造建築。
自然の力を受け止め、長い年月を超えて今もなお立ち続けるその姿に、あらためて感動しました。
次に神社やお寺を訪れたときは、ぜひ軒先にも目を向けてみてください。
きっと新しい発見がありますよ!
建物を活かして、楽しく快適に暮らす。
住宅のリノベーションをお考えなら・・・TM RENOVATION\(^o^)/
建築士とのしっかりしたイメージ共有で理想の住まいを実現しましょう!